出張前後の旅行や出張中の観光は問題ない?交通費や宿泊費についても解説
近年は、出張に合わせて観光や旅行を楽しむ「ブレジャー」というスタイルが注目を集めています。しかし、企業に所属する立場であれば本当に「出張前後に旅行をしても問題ないのか」などが気になるところです。本記事では、出張前後に旅行や観光を取り入れる際に押さえておきたい基本的なルールを解説します。
出張前後にそのまま旅行しても大丈夫?許可は必要?

出張後の旅行「ブレジャー」とは
近年、出張後に自宅や職場へ戻らず、現地に滞在して観光を楽しむスタイルが広がりつつあります。海外ではこのような休暇の取り方を「ブレジャー(Bleisure)」と呼び、ビジネス(Business)とレジャー(Leisure)を組み合わせた造語として広く使われています。
出張先で業務を終えた後に観光を楽しむことで、仕事の疲れを癒し、心身をリフレッシュできる点が大きな魅力です。日本でも観光庁や旅行会社が普及を促進しており、働き方改革の一環として注目を集めています。
「出張前後の旅行」会社ではどのような扱いになる?
一般的に、出張後の旅行は「休暇」として扱われ、当然ながら労働時間には含まれません。休暇中に発生した交通費や宿泊費、万が一の事故などは、勤務時間外と同様に本人の責任となります。
一方で、福利厚生の一環としてブレジャーを導入・推奨する企業も見られるようになっています。ただし、会社によっては直行直帰を義務づけるなど、規程でブレジャーを制限している場合もあるため注意が必要です。まずは自社の労務担当者に確認し、規程を把握したうえで旅行の計画を立てましょう
「出張中の観光」会社ではどのような扱いになる?
出張中の観光は、基本的に「休日」や「業務時間外」に行う自由行動であり、労働時間には含まれません。そのため、観光にかかる交通費や宿泊費などの費用は、原則として個人負担となります。
ただし、業務の一環として観光地を視察する場合や、顧客との関係構築を目的とした観光であれば、出張業務として認められることもあります。そのような業務目的の観光を計画する場合は、必ず事前に上司や労務担当者と相談し、正式な許可を得ましょう。
「出張前後の旅行」経費はどうなる?

出張前後に旅行を組み合わせる場合、交通費や宿泊費の精算がどのように扱われるかは重要なポイントです。会社が負担する範囲と自己負担となる費用を正しく把握しておけば、経費精算時のトラブルを未然に防げます。
交通費の負担と精算
出張後にそのまま旅行を続ける場合は、交通費の精算方法に注意が必要です。業務に伴う交通費は会社が負担しますが、出張終了後の私的旅行にかかる移動費は原則として自己負担となります。経費規定を事前に確認し、会社負担となる区間と自己負担となる区間を明確にしておきましょう。
後日精算では業務分と私的分の区別が難しくなるため、前払いまたは現金支給で処理するのが望ましいでしょう。労務・総務担当者は、出張後の旅行に関するルールを社内規定で明確にしておくことが求められます。
宿泊費の負担と精算
宿泊費についても、出張後の旅行では自己負担となるケースが一般的です。出張中の宿泊費は会社が負担することが多いですが、延泊する場合は、その分の費用をどう扱うか事前に確認しておく必要があります。
とくに、出張中と同じ宿泊施設に延泊する場合は、業務と私的旅行を明確に区別するための手続きが必要になることがあります。後日精算では業務と私的旅行の区別が難しくなるため、前払いまたは現金支給で対応するのが望ましいでしょう。
出張前後の旅行や観光について出張担当者が抑えたいポイント
出張に旅行や観光を組み合わせる際は、業務と私的行動をしっかり区別して計画することが重要です。会社の規定を確認し、スケジュールを共有することで、経費精算やトラブルを未然に防げます。
会社の出張規定を必ず確認する
出張前後の旅行や観光を計画する際は、まず会社の出張規定を確認することが重要です。規定に記載がない場合は、労務・総務担当者に相談して確認を取りましょう。会社によっては、出張後の直行直帰を義務付けたり、有休取得に「時季変更権」(※)を適用して制限したりすることもあります。
交通費や宿泊費の負担範囲、申請方法についても事前に確認しておくことで、トラブルや誤解を防げます。事前に確認を徹底すれば、出張後の旅行も安心して楽しめるでしょう。
※「時季変更権」…使用者が業務に支障をきたすと判断した場合労働者の希望した有休休暇を別の日に変更させることができる権利
出張前後の旅行スケジュールを会社と共有する
出張後に有休を利用して旅行する場合、法律上は休日の過ごし方を会社に報告する義務はありません。ただし、出張と旅行を組み合わせることで職場を長期間離れる場合は、業務への影響を避けるためにも、スケジュールを事前に共有するのが望ましいでしょう。共有する際は、日時や滞在エリアなど、業務に支障が出ない範囲の最低限の情報で十分です。
さらに、緊急時に備えて連絡手段を確保しておけば、旅行中のケガや病気、事故などにも迅速に対応できます。
仕事とプライベートの境界を明確にする
出張前後の旅行や出張中の観光では、仕事とプライベートの境界を明確に区別することが非常に重要です。経費の混同申請や、業務用物品・レンタカーの私的利用、さらにプライベートな人間関係を業務に持ち込むことは避けましょう。
規定違反は、ビジネスパーソンとしての信用を損なうだけでなく、場合によっては懲戒や税務上の処罰を受ける可能性もあります。業務と私的行動を明確に分けることで、安全かつ信頼性の高い出張を実現できます。
出張前後の旅行や観光について労務担当者が抑えたいポイント
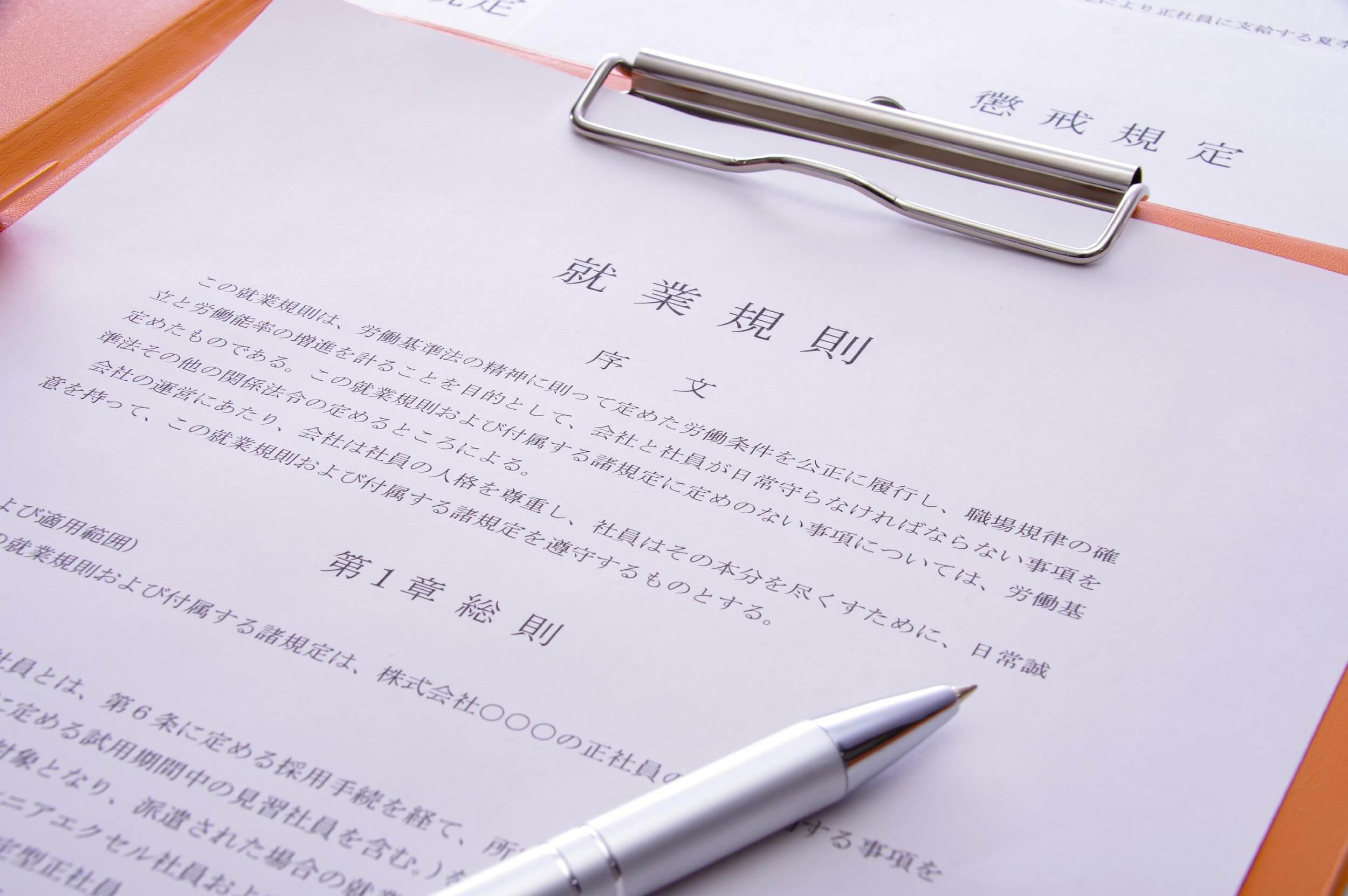
出張前後の旅行や観光を認める場合、労働基準法に沿った明確な規定づくりが不可欠です。あわせて、利用希望者の把握や不公平感のない福利厚生の整備を行うことで、社内トラブルを防げます。
労働基準法に沿った出張前後の旅行や観光に関する規定作成する
出張後の旅行は就業時間外の行動であるため、企業が一方的に禁止することはできません。労働者の私的活動に企業が介入することはできず、出張前後の有給休暇取得を一律に禁じることも原則として認められていません。そのため、労働基準法に準拠した社内規定を整備しておくことが重要です。
出張後の行動を制限する場合は、「直行直帰」のルールや「有給休暇の時季変更権」の活用など、法的根拠に基づいた対応が求められます。交通費や宿泊費の負担範囲を明記し、福利厚生としてブレジャーを認める場合には、専用の規定を設けることが望ましいでしょう。
旅行希望者を把握しておく
就業時間外の私的な行動について、企業が命令することは原則としてできません。そのため、「旅行の事前報告を義務づける」といった強制は、法的に困難です。ただし、旅行中の万が一の事故対応や業務調整の観点から、任意の事前共有が望まれます。安心して伝えられる雰囲気づくりや、報告しやすい環境の整備が求められます。
不公平感をなくす福利厚生を構築する
出張に伴う私的旅行や観光が頻繁に行われるようになると、出張機会の少ない従業員との間で不公平感が生じやすくなります。そのため、福利厚生制度は従業員間の公平性を意識して設計することが不可欠です。出張機会を公平に分配する仕組みや、出張のない部署には代替的な休暇制度を設けるなど、従業員間のバランスに配慮した制度設計が求められます。
出張後の旅行や観光についてよくある質問
出張後に旅行や観光を計画する際、よく寄せられる疑問にお答えします。労災の適用や仕事との両立、不公平感への対応など、不安を解消できる内容を整理しました。
Q.出張後の旅行中にケガや病気をしたら労災は適用されますか?
A. 出張業務終了後の旅行は私的活動とみなされるため、原則として労災保険の対象にはなりません。つまり、有給休暇や休日を利用して観光中にケガや病気を負った場合でも、業務との関連性が認められない限り、労災保険の適用は受けられません。
Q. 仕事と観光は両立できますか?
A. 近年、「ブレジャー(Bleisure)」という出張と休暇を組み合わせたスタイルが注目されており、業務終了後に観光を楽しむケースが増えています。宿泊先の延泊や移動スケジュールの調整などを工夫すれば、出張後に休暇を楽しむことも十分可能です。
なお、仕事と休暇を同時に行う「ワーケーション」とは異なり、ブレジャーは業務終了後に私的な時間を設けるスタイルです。
Q.出張がない従業員に不公平だと言われたらどうすればいいでしょうか?
A. 総務・労務担当者の立場では、出張や観光の機会に偏りがある場合、不公平感を軽減するために休暇制度や福利厚生の充実を図ることが重要です。たとえば、出張のない部署に対してはリフレッシュ休暇や代替的な福利厚生を設けるなど、制度のバランスを取る工夫が求められます。
出張担当者の立場では、業務内容や人員構成を踏まえつつ、出張機会が特定の従業員に偏らないよう公平に配分することが求められます。
出張も快適!アパホテルで過ごす至福の時間

アパのリゾートホテルでは、大浴場を完備しており、ご宿泊の方はもちろん、日帰りや外来でもご利用いただけます。出張で慌ただしい一日を終えた後、広々とした大浴場で疲れを癒し、リフレッシュできる空間を提供いたします。都会での仕事の合間に、心身を整えるひとときをお過ごしいただくことも可能です。快適なビジネスライフをサポートする場として、ぜひアパのリゾートホテルをご活用ください。
出張後の旅行・観光を安全に楽しむにはルールの把握が重要
出張前後の旅行や出張中の観光は、労務規定や経費精算のルールを正しく理解して計画することが重要です。交通費や宿泊費の負担範囲、業務と私的活動の区別、社内での情報共有などを押さえることで、トラブルを防ぎつつ安心して旅行を楽しむことができます。総務や労務の担当者は、制度整備やルールの周知が安全・円滑な出張運営の鍵となることを覚えておきましょう。

この記事の監修
アパホテル株式会社
◯事業内容
アパホテルネットワークとして全国に900ホテル以上(建築・設計中、海外、FC、アパ直参画ホテルを含む)を展開している。
また、2,200万人を突破したアパホテル会員を背景に、全国のネットワークを強固するとともに、くつろぎと洗練さをあわせ持つ「新都市型ホテル」や地方ホテル再生、フランチャイズ等で積極的に事業を拡大しています。







